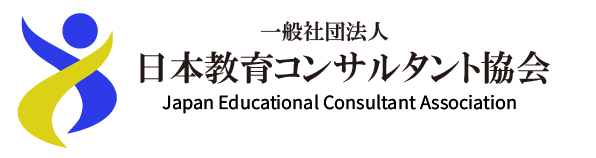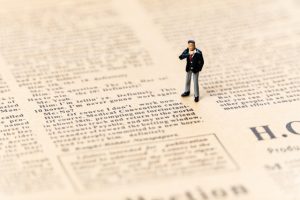学習指導要領を抜本から見直すことが必要ではないか?
通知表の評定は年1回に?次期学習指導要領で変わる成績付け(朝日聞9月29日)
次期学習指導要領の論点整理で示された大きな変更点の一つが、通知表の「5」などの評定につながる評価だ。評定付けの元になる三つの観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」については、ABCなどと表さず、評定にも含めない形に変わりそうだ。
東京都世田谷区の区立桜丘中学校。多様な子どもたちに応じた柔軟な教育をする学校として、コロナ禍前に、校則をなくし、チャイムを朝1回だけにして、定期試験も廃止した。その後、校長が2人交代。チャイムは毎時間に、定期試験も復活した。ただ、別室や校長室、職員室前の廊下の机には、いまも教室に入りづらい生徒らが集う。
全生徒の1~2割は不登校ぎみだ。40人程度は、授業はもちろん定期試験でも、キーボード入力や音声読み上げ、ルビを振った問題用紙などを活用する。試験も一定の期間内の後日受験や、時間延長、別室受験も認めている。
山本武校長は毎春、保護者会で各教科の成績の付け方を資料を配って説明してきた。
「うちの学校では、授業中の積極的な発言など、性格や表面的な行動で『主体的に学習に取り組む態度』を評価することはしません」と断言する。3観点のうちの他の二つ、「知識・技能」「思考・判断・表現」の定着度を踏まえ、生徒自身が学習を計画、改善しようとしているか、などで評価するという。「全く挙手せず、ノートも書かなくても、ちゃんと考え、理解している子もいる。表面的な行動で評価するのは、強制にもつながり意味がない」と山本校長。
漢字を繰り返し書くような課題も出さないよう、教員に伝えている。10回書かないと覚えられない子も、1回見て覚えられる子も、書くのが苦痛な子もいるためだ。評定の成績付けの材料となる、定期試験と提出物などの割合は各教員に任せているが、ノート提出の評価は補完的なものとしてしか扱わない形にした。「次の指導要領で『態度』を所見欄だけにするのは、生徒にも、教員にも良いこと」と歓迎する。
同校では、不登校でも、定期試験を年2回ないし3回、後日でも受け、提出物の6割程度を出せば、評定は斜線や空欄にしない方針だ。一方で「絶対評価だからオール5に」「学校のせいで不登校になったのに成績が下がるのはおかしい」などと言う保護者もいる。山本校長は「平等とは何か。多様性を包摂する評価は、保護者への説明がより重要になる」。
通知表を全廃した東京都新宿区立西新宿小学校の長井満敏校長も「保護者の意識改革が必要」という。保護者面談の際に、学級での順位や成績を教えてほしいと求める保護者も少なくなく、担任が別途資料を作り対応することもあった。子どもたちは「(親が)面談から帰ってきたら、いきなり怒られた」とこぼす。
文部科学省が学校に作成・保管を義務づけている学習評価は、小学校から中学、中学から高校へと引き継がれる、各児童生徒の「指導要録」の学年末1回分の「評定」しかない。「通知表」は、その項目を使い現場が各学期末に慣例的に作成するものにすぎない。
これまで学習評価は、学習指導要領の目標・内容に照らした到達度を、1知識・技能2思考・判断・表現3主体的に学習に取り組む態度の3観点ごとに3段階で評価。総括して、各教科の「評定」を小学校3段階、中学高校5段階で表した。3は挙手回数やノート提出などではかるものではないと国はしているが、保護者に説明できる客観性を持たせるため、材料にする教員も少なくなかった。
結果的に、発言が苦手な子、読み書きが苦手な傾向の子らに、苦手なことを強いることにもなった。
中央教育審議会特別部会の論点整理では、3は評定の材料に含めず、「個人内評価」として所見欄に書く、特に良い場合には「○」などを付けて補助的な材料にする、などの方向が示された。また、次の指導要領で▽中核的内容に精選▽「裁量的な時間」に教科の基礎・発展学習を行う可能性▽不登校や特異な才能のある子らへの特例的な教育課程を行う──などの改革により教育課程全般を踏まえた評価も必要とした。教員の負担軽減や柔軟な教育課程を前提に、評定も指導要録と同じ学年末1回のみにすることも示されている。
学習指導要領は、日本のマンパワー政策の変化によって変わってきた。1980年代後半に、日本のマンパワー政策は、アメリカ、イギリスの外圧によって、日本教育の弱体化に舵を切り、その後、どんどん後退して、今日に至っている。1980年代の貿易摩擦が引き金になって、アメリカ、イギリスが日本に圧力をかけ、日本の教育は弱体化していくことになったのだ。いわゆる、レーガン・サッチャー・中曽根、三者会談による合意が成立したのだ。日本の教育は、1990年代から大きくカーブを切って、ダメになっていった。そして、その終着点が、2002年のゆとり教育なのだ。
その後、学力問題が教育問題になり、学習指導要領は、徐々に内容を以前のように戻していくが、その教授法は、学力を形成することへシフトするのではなく、子どもの主体性という名の無責任な指導へと移っていくのだ。そして、その評価の象徴が、観点別学習状況評価なのだ。それこそ、新学力観として、1990年代の学習指導要領では、「関心・意欲・態度」という主観的であいまいな観点が最上に置かれて、約30年間評価の軸になっていた。そして、2020年からの学習指導要領でも表現を変えて「主体的に学習に取り組む態度」として残ったのだ。
今回、とうとう「関心・意欲・態度」という主観的であいまいな観点の残骸である「主体的に学習に取り組む態度」が、評価の軸から消えることになるのだが、この際、学習指導要領全体をもう一度見直して、どういう人間を育て、そのために、どういう教授法をとればよいのか、しっかり見直すことだ。アメリカ、イギリスの楔を断って、抜本的に考え直した方が良い。だからと言って、安倍政権であったような産業界を中心にした教育再生会議のような似非教育論を振りかざす産業界の人間など入れないで、教育をしっかり思考できる現場の人間と専門家(御用学者ではなく)で構成された諮問委員会を作って、日本の教育について考えた方が良い。
日本の基礎基本として、教育という観点から学習指導要領を抜本的に見直しを行ってほしい。
一般社団法人日本教育コンサルタント協会
代表理事 中土井鉄信