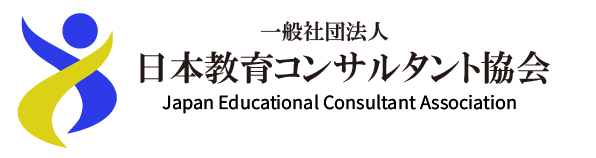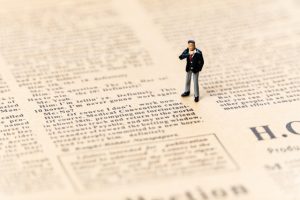意味のないことに意味があるとしたら!
駿台予備校、大学合格者数の公表を終了 「数字が形骸化、意味なく」(朝日聞8月1日)
大学合格者数の公表やめます――。
大手予備校・駿台予備学校が、今年度実施の入試から大学合格者数の公表をやめる。運営する駿河台学園(東京都)が1日、発表した。
学園は、理由に、オンライン学習が普及し、複数の塾や予備校を掛け持ちする形となっている生徒が多いことを挙げた。各予備校が公表している合格者数を合計すると入学定員を超えており、予備校ごとの成果が分かりづらくなったと説明する。
また、合格者数は予備校選びの指標だとしながら、「数字が形骸化し、意味をなさなくなっている。それぞれの第一志望がある。色んな人に門戸を開いていると伝えたい」とした。
駿台予備学校は「第一志望は、ゆずれない」のキャッチフレーズで知られ、河合塾、代々木ゼミナールとともに三大予備校といわれる。ホームページによると、昨年度の合格者数は東京大1351人、京都大1422人。
この記事を読んで、2000年前後のある出来事を思い出した。中学受験の日能研が、合格実績をチラシでアピールすることを決断したことだ。この決断の結果、中学受験の合格実績は、サピックスにどんどん抜かれることになった。偏差値教育に意味はない。よって、どこに何人受かったかなんて意味はない。そういう想いで日能研は、合格実績をアピールしなくなったと記憶しているので、今回の記事を読んで、駿台予備校のこの先進的な試みは、約25年前の日能研の試みと同じになるのかどうなのか、ちょっと気になったのだ。
記事にあるように、各予備校の公表している合格者数を合計すると入学定員を超えているなんてことは、何十年も前から言われていて、それでも、予備校選びの指標として合格実績はあったのだ。数字が形骸化しているとか、意味をなさなくなったとか、そんな理由でこの指標をほかの予備校の先陣を切って廃止しても、あまり意味はないのではないか。逆に、意味のないことだからこそ、ある一定の意味を帯びてしまうのではないか。
東大に一番近い予備校は、駿台だったはずだ。その東大の合格実績の数を公表しないということは、大きな意味を持つ。まさに、他の予備校に抜かれてしまうから公表しないのだという意味と、そんな次元では勝負しないのだという意味だ。
しかし、予備校は、生徒の精神的な成長を問うところではない。予備校はそういう意味で学習塾以上に目的が明確なところだ。大学合格が、何にもまして重要な目的なのだ。その結果を公表しないということの意味は大きい。駿台の決断がどうでるか。注目したい。
一般社団法人日本教育コンサルタント協会
代表理事 中土井鉄信