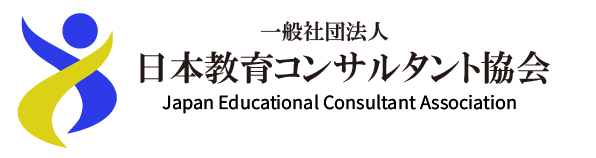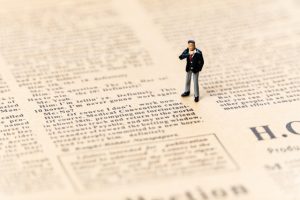これまでの改革を総括して次に進むべきだ!
学習指導要領の改訂へ、文科相が諮問
柔軟化、負担軽減がポイントに
(朝日新聞12月25日)〇2030年度にも導入される小中高校の学習指導要領の議論が25日、始まった。
20年度以降に導入された今の指導要領がめざす「主体的な学びの実現」などの方向性は維持しながら、多様な子どもへの対応やデジタル時代にあわせた教育、教員の負担軽減を図る内容をめざすことになる。
〇阿部俊子文部科学相が25日、中央教育審議会(会長=荒瀬克己・教職員支援機構理事長)に諮問した。
〇学習指導要領は、文科省が決める教育目標や内容で、学校で教える最低限の基準。約10年に1回の頻度で改訂されてきた。
〇これからの審議を受けて決まる新指導要領に基づく授業は、小学校が30年度、中学が31年度、高校が32年度以降に始まる見込み。
〇文科相が検討を求めた主な内容は、学校ごとの教育課程の柔軟化
▽情報モラルやメディアリテラシーの育成
▽教科書の分量や年間の標準総授業時数(コマ数)――など。〇今回は、「ゆとり教育」や小学校での英語教科化などにつながった過去の改訂と違い、
https://www.asahi.com/articles/DA3S16085907.html
大きな制度変更は想定されていない。
〇一方、学校では近年、不登校や日本語指導が必要な子ら
個別の対応が必要な児童生徒が増えている。また、生成AIの普及もあり、
画一的な知識教育ではない主体的な思考力の育成が強く求められている。
〇このため、学校現場の実情にあった柔軟な指導をどう促すかが焦点となる。
具体的には、各校の裁量で、例えば1コマの時間を5分短くして余剰時間を独自の学習に充てたり、教科横断型の授業をしたりしやすくする仕組みなどが検討される。(省略)
◇学習指導要領は、学校教育の憲法だ。
この憲法を大幅に変えたわけだから、その総括をして、部分改定にするのか、大幅改定にするのか、議論をした方が良いと思うが、文部行政は歴史上、ほとんど総括という作業をしてこなかった。
今回の学習指導要領でもそうだ。
子どもたちは、「活動」しているが、「学んで」いないという状況が報告されていたり、教師の実感として、学ぶ代わりに活動をして時間をつぶしているという報告もあったりしているが、それについては、どう検討するのか、まったく見えない。
◇子どもが主体的に学ぶということと、活動しているということが混同され、学び合いは、ジグソー学習をしていれば、それで良しという感じだ。
各自が分担されたところを調べて発表したところで、全体像を理解することなんぞ、なかなかできないのが実情だ。それでも、よく活動したという評価になってしまう。
これでは、子どもたちが何を得るのか。まったく不明なのだが、学習指導要領に「子どもの主体的学び」とあるから、やめられないということなのだろう。
もっと地に足を付けた教授法に戻るべきだ。
そうしないと、表面的な知識の獲得と疑似的な主体性もどきの活動で終わってしまう。
◇子どもの学力格差をどうするのか、ここも議論をするべきだ。
全国の定期テストの結果を文部行政にはみてほしい。
二極化が、平均点以下で生まれているのだ。
このような状況を生んだ可能性のある学習指導要領をしっかり総括することだ。
そうしなければ、あまりにも無責任ではないか。総括をしてほしい。
一般社団法人日本教育コンサルタント協会
代表理事 中土井鉄信