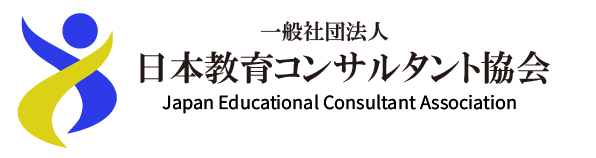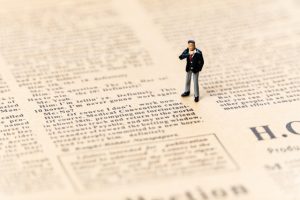教育は、”最小の努力で最大の結果”を求めてはダメだ!
「デジタル教科書」を正式な教科書に 学びは進化? 課題もいろいろ(朝日聞9月24日)
「デジタル教科書」が、正式な教科書となる方向性が固まった。これまでは教科書の代わりの教材という位置づけだったが、小中学生への無償提供や、国の教科書調査官による検定の対象となる。「学びの充実につながる」とされる。ただ、細かな点は、これから話し合われる部分が多い。
中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)の作業部会が24日、約1年間の審議のまとめを示した。これを受け、文科省が詳細に検討する。文科省は、来年に関連法が改正される日程を想定。来年度中に発行や使用の指針をつくり、2030年度にも変わる次の学習指導要領に合わせて学校に導入する予定だ。
教科書は、今は紙だけ。それを、
1.デジタルのみ、
2.デジタルと紙の組み合わせ(ハイブリッド)、
3.紙のみ──の3種類を認める方向性を示した。
このうちデジタル教科書と呼ばれるのは1と2。文科省は、制作費などの理由で2が多くなるとみる。
デジタル技術を活用すると、子どもの特性にあわせた学びが実現できる。文字の拡大▽音声の読み上げ▽ルビ振り──などの機能が一例だ。
今「デジタル教科書」と呼ばれている教材にもこうした機能は備わっている。ただ、中身は紙の教科書を電子化した「電子書籍」のようなもの。作業部会や文科省は、機能に加え、デジタルならではの内容を多く採り入れ、教育内容を充実させようと考えている。例えば、単語をフラッシュカードのように音と映像で見せる(英語)▽プログラミングのやり方を動画で見せるだけでなく、実際に打ち込んで簡単な動作を見せる(情報・技術科=仮称)▽図形をアニメーションで動かす(算数、数学)▽紙では見開きの内容をスライド形式で順に表示(各教科)──などだ。
2019年にGIGAスクール構想が打ち出され、22年度末までに、ほぼ全小中学校で1人1台のタブレット端末が配られた。通信環境とともに学校のデジタル環境が大きく進んだことも、デジタル教科書を広げる背景にある。
では、どんなデジタル教科書になるのか。その形はよく見えていない。文科省が最も普及するとみる「デジタルと紙の組み合わせ(ハイブリッド)」について、審議まとめでは「一部が紙、一部がデジタル」という表現にとどまった。
文科省の担当者は「教科書会社が創意工夫できるように、自由度を高めたい。紙とデジタルのバランスや組み合わせ方は自由」と説明する。例えば、▽基本は紙で必要なところはQRコードからデジタル素材につながる▽単元ごとに「デジタルで学ぶ」「紙で学ぶ」と分ける▽デジタル素材を見られるアプリを端末に入れて紙と併用──などが考えられる。
今の紙の教科書にも、デジタル素材につながるQRコードが多数載っている。ただし、検定対象ではないため内容は様々。今後は、教科書についたQRコードから見られるデジタル素材は検定の対象とし、作業部会や文科省は、質・量ともに厳選したい考えだ。デジタル部分が増えれば今より情報量が膨らむ可能性がある。また、最新の情報に随時更新することも考えられる。そのため、検定の方法も今後、専門家の会議で話し合う予定だ。
今の「4年に1回」が適切かどうか、動画が長くなりすぎないように時間の基準が必要かどうか、などが論点となる見込みだ。
デジタル教科書が、導入されようとする時、私はテレビ局の取材を受け、学びは「人と人の中にあるのであって、それを教科書で完結しないほうが良い」と答えた。だが実際にニュースで放映された時は、その発言はカットされ、デジタル教科書は、操作性が面白いと言ったところが切り抜きになって放映された。非常に驚いたことを今でも覚えているが、今回の中央教育審議会の結論は、3択を用意したという点で、ギリギリセーフのものだ。
デジタル教科書の弊害は、北欧でも指摘されている。そして、北欧では、デジタル教科書を見直す動きがある。それを今更、デジタル教科書も教科書だと認めるのは、どうしたものかと思うが、百歩譲って、紙とデジタルのハイブリッドなら、仕方がないと思う。デジタルでやる方が良い場合もあるからだ。
しかし、今回の結論には、実に日和見だとも思う。世相に沿った形を取り入れたとみられても仕方がない。なにせ、デジタル教科書では、学力は上がりにくいと北欧の実践で指摘されているのだから。
新しいことをやればよいというわけではない。子どもに苦労をさせて、学ぶ魅力を知ってもらうことも重要だ。本当のことは努力しないとわからないと実感してもらうことも重要なことだ。教育は、最小の努力で最大の結果を求めてはダメだ。世間はそんなに甘くはないのだから、最大の努力で最小の結果しか出ないということを、もっと子ども時代に教えた方が良いのだ。そういう意味でも、デジタル教科書は、要注意な代物なのだ。
一般社団法人日本教育コンサルタント協会
代表理事 中土井鉄信