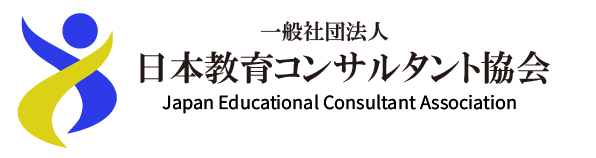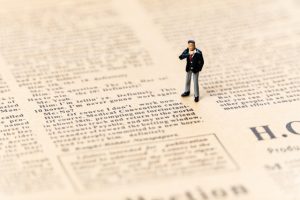誰のために、無理をするのか?暗黙の理想を捨てるべき時だ!
部活、遠征…53日間で休み1日 教諭の過労死「美談にしたくない」(朝日聞6月26日)
富山県滑川市の市立中学校で理科を担当していた当時40代の男性教諭は、授業と子どもが大好きだった。
妻と歩いていても、生徒に受粉のしかたを見せるのにツユクサの花はないかと探した。管理職の試験を受けず、一教員として生涯、子どもと関わりたいと言っていた。
担任をしていたクラスは、やんちゃな男子が多かった。生徒が日々の出来事や思いを書いたノートにコメントを書き、声かけを重ねた。そんな丁寧な対応が、生徒や保護者の信頼を集めた。
それだけではない。ソフトテニス部の顧問として多忙を極めていた。平日は朝と放課後に練習があり、顧問として指導にあたった。練習後は夜7時過ぎ頃から、授業で使うプリント作りや実験の準備に取りかかった。帰宅後は幼い子どもに本の読み聞かせをし、風呂に入れてから、深夜まで授業研究に取り組んだ。
公立中学の教員は、多くが部活動の指導に携わってきた。文部科学省の2022年度の教員勤務実態調査によると、中学で部活動の顧問をする教員は8割を超えていた。週当たりの活動日数は「5日」が56.1%。日数が多いほど勤務時間が長い傾向も浮かんだ。
滑川市立中学の男性教諭は、休日は部活の試合や遠征で、しばしばつぶれた。ベテランの顧問が抜けたばかりで休みたくても休めないようだった、と妻は言う。
「夏休みになったら、人間ドックにいくから」と言っていた矢先の7月22日未明。寝ていた男性は、うめき声を上げ、意識を失った。そのまま意識はもどらず、8月9日に亡くなった。くも膜下出血だった。妊娠中だった妻と、当時2歳の子どもが残された。
男性は発症前、53日間で1日しか休んでいなかった。妻は「過労死なんて考えも及ばなかった」と悔いる。「夫のことを美談にしたくない。頑張る先生が同じ目にあってほしくない」。
17年、妻は地方公務員災害補償基金県支部に「公務上の災害」だと申請し、翌年、認定された。
19年には、夫の死は、過労で健康を損なわないように注意する義務(安全配慮義務)を校長が怠ったためだとして、県と市に計約1億円の損害賠償を求める訴えを富山地裁に起こした。
「夫が亡くなった責任がどこにあるのか知りたかった」と妻は言う。公立学校の教員には、1971年にできた「教員給与特措法」(給特法)という法律がある。この法律によると、学校行事や職員会議などについては校長が時間外労働を命じられるが、それ以外は命令を出せない。このため、多くの残業は教員の自主的、自発的な労働と解されてきた。
https://www.asahi.com/articles/AST6R3W04T6RUTIL005M.html
「残業時間がいくら長くても、誰も責任を問われてこなかった」と裁判を担当した松丸正弁護士は言う。(中略)
公立学校教員の時間外勤務に関しては、文科省が19年に「月45時間以内」「年360時間以内」というガイドラインを設け、後に指針とした。しかし、なかなか守られていないのが実情だ。
この記事には、6月22日から7月21日の残業時間の表がある。1か月の残業時間が、119時間強。1か月45時間が残業時間の目安だとすると2倍以上、100時間が最大だとすると、20時間弱超え出ている。
また、記事によれば、自宅でも授業準備に時間を使っていたようなので、実質業務は、随分と長かったようだ。
なぜ、この教師は、そこまでして自主的に残業をしたのか。ここが問題なのだが、それは、想像するに、暗黙の期待に応えるためにではないか。生徒からの期待、保護者からの期待、そして、自分自身が持っている理想の教師像に応えるために、がんばったのではないか。自分の命を削ってまで仕事をすることはないのだが、暗黙の、現実的に何もない期待や理想を背負ってしまったのではないか。
客観的に自分を俯瞰できたら、このような事態にはならなかったのかもしれないが、ある種の暗黙の圧力が、教師にはかかりやすい。子どもが頼むから。保護者が要望しているから。相手の期待に応えてこそ良い教育は出来るのだ。そのような想いになりやすい職業が教師なのだ。このことを私たちは、自覚しておいた方が負い。
教師も人の子だ。そのことを前提に教師像を再構成していくことが、大切なことだ。
一般社団法人日本教育コンサルタント協会
代表理事 中土井鉄信